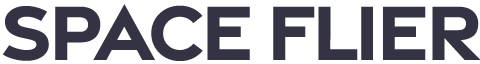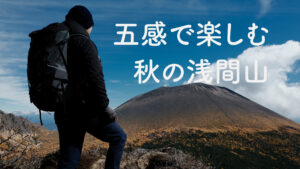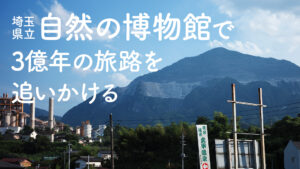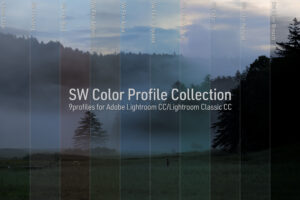当サイトは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
圧倒的な岩石の圧力 大谷資料館

Hiさんの記事を読んで「面白そう!」ということで大谷資料館に行ってきました。天気もいまいちすっきりしないし調べてみたら2時間弱で行けるみたいだし。
大谷資料館についての詳しいことはHiさんの記事をお読みいただければと思います。1点注意しておいた方がいいのは高感度に強いか手ブレ補正が強力か、またはその両方を備えたカメラを持っていきましょうということです。スマートフォンのカメラではまず無理でしょう、というほどの暗さとコントラストの激しさ。パワー is 正義な場所でした。

ちょっと遠回りしてみるのも面白い
資料館前の駐車場に車を停めたHiさんとは反対側の大谷駐車場へ車を停めて、ちょっと大谷資料館まで少し遠回りしてみることにしました。といってもたかだか750mほど。周囲を見回しながら歩いていればすぐ着く距離です。

大谷石の産地ということで当然ながら石畳も大谷石。

歩きながら目を横にやるとそこかしこに岩が穿たれた跡を見ることができます。採掘場跡に入る前からなかなか異世界感を醸していますね。

日常の中に聳える岩の壁。もちろん採掘の跡です。
坑道内へ

さて、この日はそれほど暑くはありませんでしたが坑道に入ると確かに奥から強い冷気が噴き上げてきます。

最初の踊り場につくと見慣れた(というのも変ですが)アングルの撮影ポイントでした。Hiさんの写真では割と明るく見えていたのですが、実際にその場に立ってみるとかなり暗いなかに強い照明が設置されていて露出設定が難しいですね。
冒頭でも書きましたが、これはスマートフォンじゃどうにもなりませんね。そこら中から「無理だな〜」とか「フラッシュいるかな」なんて声が漏れ聞こえてきます。

一番下まで下りると立体作品が展示されていました。
それにしてもこのシチュエーション、 #手持ち長秒チャレンジ をしろと言わんばかりの環境です。もちろん思う存分チャレンジしましたよ。

といっても、適宜ISO感度は上げますしシャッタースピードや絞りの選択肢を増やすという意味で、ですが。ところでこの写真を見て実際に行かれた方は「あれ?」と感じるかも知れません。ここはもともと飽和するほどの青い照明が当たっているのですがRAW現像していると「ちょっとキツいな・・・」とニュートラルな色味になるように調整しました。
ライトアップに多いピンクや紫などの超高彩度のものはどうにも苦手なんですよね。人工物に対してであればわからなくもないところなんですが、滝や雪景色などの自然物に対しては正直理解に苦しみます。
ディテールが面白い

ちょっと愚痴っぽいことを書いてしまいました。しかし、この巨大な坑道には目を引く面白いディテールがそこかしこに見られます。
この縦穴、通気口だそうでHiさんの写真では超広角ズームで撮影されていたのですが、実際に見ると予想していたよりはるかに大きくて驚きました。

その中でも個人的に面白いなと感じたのがこの展示。大谷石の外構(塀)のサンプルです。展示室にも各種のサンプルがありましたが、目の粗さなどの違いがあるようですね。
印象的な光

ところで今回の中で最も長いシャッタースピードになったのはこちらの1枚。奥の地上の光と手前の地面をなんとか収めようと設定を試していたら15秒ということになりました。肘を預けられる構造物があったればこそですが、三脚無しでここまでの設定を試せるというのは本当に大きな武器になりますね。

こちらはほぼ光のない方向。水の中にライトが1つ浮かんでいるのだけしか見えず長秒露光をすれば何か見えるだろうと撮ってみた1枚です。

最後はHDRで遊んでみました。先ほどの15秒の1コマと同じ坑道をより地上近くのポジションから撮っています。この資料館になっている坑道はまだ現役で採掘している場所もあるそうで、どうやらこの坑道から車が出入りしているようです。
ちょっと寄り道

大谷資料館に訪問する前、ちょうどお昼頃の到着だったため近くで昼食をと思ったらぎょうざの正嗣 駒生店がありました。1人前210円ということで相変わらずの人気です。

ちなみに店内の招き猫はブラック労働を課せられているようです(冗談です)。