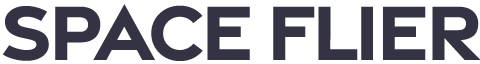当サイトは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
オールドレンズを蘇らせる!MFレンズ分解メンテナンスに役立つ市販&自作ツール

仕事先で「処分するつもりだから」と譲り受けたレンズを蘇らせたい──そんな想いから、一眼レフ用のMFレンズの分解メンテナンスを始めた。以前から興味はあったものの、本格的に取り組んだのは2025年に入ってから。まずは曇りやカビのある難ありレンズを手元に集め、必要なツールを揃えてメンテナンスに挑戦することにした。
オールドレンズが抱える問題
オートフォーカスが主流となって30年以上、一部のレンズを除きマニュアルフォーカスレンズの大部分はいわゆるオールドレンズと呼ばれる40~60年(ものによってはさらに古い)年代物だ。それだけの時間を経れば、大切に保管されていたものでもなんらかのトラブルを抱えていても不思議はない。
オールドレンズの主なトラブルは、大きく以下の3つに分けられる。
- 前玉または後玉のキズ(修復が難しく、基本的には交換以外の手段がない)
- レンズ面のカビや曇り、チリの付着(バルサム切れは修復困難だが、表面のクリーニングで改善する場合も)
- ヘリコイドや絞りのグリス劣化(適切なメンテナンスで新品同様の操作感を取り戻せる)
1番目のキズは、同型のレンズからパーツを流用するなどの手段があるが、基本的には修復困難だ。2番目のレンズの曇りについては、バルサム切れの場合は手が出せないが、表面のクリーニングで写りを改善できることがある。そして3番目のグリス劣化については、正しい作業を行えば劇的に操作性が向上する。本記事では、主に2番目と3番目のメンテナンスに必要なツールを紹介する。
市販ツール
まずは市販ツールから紹介する。模型や工作を趣味にしている人なら既に持っているものもありそうだが、レンズサッカーなどはレンズメンテナンス特有のツールかも知れない。
精密ドライバー
レンズ分解には、以下の精密ドライバーが必要になる。
私はKTCの精密ドライバーセットと、セットには入っていないマイナスの1.0mmを別途用意した。特に小さなイモネジを扱う際は、先端精度が高いものを選ぶのが重要だ。
| プラス | PH00、PH0、1P |
| マイナス | 1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm KTCのセットでは1.5mm〜2.5mmが含まれるため、1.0mmのみ別途購入 |
レンズ分解ツール
精密ドライバーの他に必要な分解ツールはジャパンホビーツールから「オールドレンズ メンテナンスキット」というそのものズバリのセットが販売されている。これはカニ目レンチとしても使えるコンパス、レンズを吸盤で掴めるレンズサッカー、銘板などを外すためのレンズオープナー、クリーナー液を微量だけ吸い出せるハンドラップがセットになっていて、最低限レンズを分解するツールが揃えられる。
とはいえ、これだけでは本当に最低限なのでよりスムーズに作業するためにいくつか買い足したいものがある。
逆作用ピンセット
小さなイモネジなどを組み戻すときにあると便利。逆作用なので手を離すと閉じるのでネジの位置合わせに集中しやすい。
ヘッドルーペ(拡大鏡)
レンズに使用されるネジはとても小さいので両手がフリーになる拡大鏡があると劇的に楽になる。自立式でもヘッドマウント式でもいいが、ヘッドマウント式の方がいちいち位置を調整しなくていいので使いやすい。
小さめの差し金とけがき針、各色油性マーカー

ヘリコイドの分解時に「合い」の位置をけがくのに使う。分解前に無限遠や最短合焦位置のマークをしておかないと組み戻しの際、どこが正解だったのか何度もやり直して手探りするハメになる。けがくだけでもマーキングとしては十分だが、ホワイトやレッドのペイントマーカーでインクを入れておくと分かりやすい。
ブロアー
VSGO タンブラーエアーブロアー。吸気口にフィルターが付いているため、吹き出し口からホコリが出ないので、せっかく清掃したレンズに新たなホコリが付くのを防げる優れものだ。
自作ツール
続いては自作ツールの紹介だ。市販のツールでは対応できないものを3Dプリンターで自作している。
大径レンズオープナー

ジャパンホビーツールのメンテナンスキットに含まれるレンズオープナーでは対応できないサイズの化粧リングを回すため、3Dプリンターで専用ツールを自作した。試作のつもりでNIKKOR-S Auto 50mm F1.4のフォーカスリングに合わせて設計したが、結果的にPENTAX 67用レンズの化粧板にも対応できたため、汎用性があることが分かった。
PETGフィラメントで造形した筒の先端に2mm溝のラバーを貼り付け、しっかりと力をかけて回せるよう設計。筒の厚みはラバーを被せる先端を除き4mmとし、側面には滑り止めの溝を彫っている。
クリーニングスティック

ふたつめは奥まった箇所やレンズの縁を吹き上げるためのクリーニングスティック。エッジを丸めた台形状のヘッドをクリーニングペーパーでくるみ、柄に付いているストッパーで挟み込んで使う構造になっている。ペーパーの交換は若干手間だが、センサークリーニング用のスワブを使い捨てるのに較べれば、大した手間でもないしはるかに経済的だ。
ネジ・ツールトレイ

GridfinityというZack Freedman氏によって提案された、3Dプリンターで作る収納システムに対応させたネジやツールトレイを作ってツールワゴンの引きだしを整備している。
まだ、発展途上なので埋まっていない枠があったり不揃いな部分もあるが、ステップネジトレイ(写真右下あたり)は気に入っている。階段状にネジ受けを配置しておくことで、分解順にしたがって外したネジを分類しておける。小さくて似たようなネジが多いので単純な仕組みながら記憶に割くリソースが減らせるというのが良い。
クリーニングペーパーやドライバーのトレイなど、ケースからいちいち出し入れすると面倒なものを定位置を決めつつサッと取り出せるように配置している。
消耗品
ここからはペーパーやクリーナーなどの薬品類の紹介だ。
無水エタノール
油分やホコリの除去に使用している。レンズ表面には拭き跡が残りやすいので仕上げには専用のレンズクリーナーを併用している。使う頻度が高いのでハンドラップに入れてすぐ使えるようにしてある。
レンズクリーナー
HCLやハクバ、フジなど状況に合わせて拭き跡が残らないものを使っている。オリンパスが販売していたハイパークリーン(EE-3310)の後継品も評判が良い。
キムワイプ
ホコリや毛羽立ちが少ないクリーニングペーパー。やや目が粗いので外装の汚れ落としに使う。
ダスパー
より目の細かい柔らかいクリーニングペーパー。レンズ表面の汚れ取りに使う。そのままのサイズでは大きすぎることと、大量に消費するためコスト削減を兼ねて80x300mmのペーパーを半分に切って使っている。元々使っていたHCLのクリーニングペーパーがちょうどそのサイズだったというのも理由だ。(レンズ面の拭き取りは一回ごとに使い捨て)
ヘリコイドグリス
ジャパンホビーツールのヘリコイドグリスの#40と#500を使用している。この組み合わせは少し重めの操作感となるので、コシナレンズのような滑らかさが欲しい場合は#30より柔らかいものが適しているだろう。
道具は揃った。あとは手を動かすだけだ。

レンズ整備は決して難しいものではない。最初は戸惑うこともあるが、手を動かしながら仕組みを理解していけば、確実に経験が積み重なっていく。曇ったガラスがクリアになる瞬間、固着していたリングがスムーズに回る感触。そうした小さな変化が、分解メンテナンスの醍醐味だ。
大切なのは、焦らず慎重に作業を進めること。そして、試行錯誤しながら自分なりの整備の流儀を見つけていくことだ。
まずは手元の一本から、試してみよう。